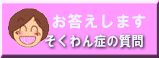連載第3回 「早めの装具 悪化を防ぐ」
読売新聞の「医療と介護」覧の中の「医療ルネサンス」にて、2006年2月14日~18日までの5回、脊柱側弯症に関する記事が連載されました。当時掲載された「医療ルネサンス」からの転載記事です
医療ルネッサンス

先月中旬、聖隷佐倉市民病院(千葉県佐倉市)の診察室で、近くに住む小学6年生C子さん(12)はおびえていた。傍らに立つ母親の手を握り、勇気を振り絞って医師に質問した。
「自転車に乗れますか」
「体育はできますか」
「外見は変わりますか」
脊柱(せきちゅう)側わん症で背骨のわん曲が30度を超え、プラスチック製の装具による治療が必要になった。装具への不安は大きい。
主治医の同病院副院長、南昌平さんは、やさしく答えた。「日常的な動作も、体育も、ほとんど問題なくできるよ。水泳の時は、はずしてもいいからね。服を着ればわからないよ」。母親と見つめ合い、うなずいた。「頑張って付けてみよう」と思った。
装具治療は通常、わん曲が25度以上、45度未満で成長期の子どもが対象だ。背骨を10度ほど戻し、装具で固定する。わん曲を大きく矯正する効果 はないが、それ以上の進行を抑えることができる。成長が止まる17~18歳ごろまで、入浴時と激しい運動時以外は、就寝中も含めて常に着用する。
以前は、首から骨盤までを覆う方法が一般的で、襟元から装具が顔を出すことに患者の抵抗感は強かった。現在は、改良が進み、腕から下だけの装具で も、ほぼ同じ効果が得られるようになった。また、圧迫個所を背中の隆起など必要最低限にする工夫で、締め付けられる不快感や動きの制約は減っている。
装具は、一人ひとりの体形に合わせ、義肢装具士らが作製する。同病院の装具では、着用によるウエストサイズの増加は約8センチ。服のサイズを一回り大きくする程度で納まる。
同病院の側わん症外来では、診察室の隣に義肢装具士2人が待機。患者から装着感を聞き、「痛い」「苦しい」などの訴えがあれば、装具の角を丸くし たり、中にパッドをあてるなどの微調整を行う。義肢装具士の岩下幸男さん(67)は「要望を良く聞いて、心身の負担を少しでも和らげてあげたい」と話す。
体に合わない装具では十分な効果が得られず、痛みがあれば継続が困難になる。気になる点があれば、遠慮せずに、医師や装具士に伝えるようにしたい。
側わん症は、体操などでは治療効果が得られないとされ、装具治療が手術を避ける唯一の防波堤となる。
南さんは「わん曲を小さく抑えるには、25度を超えて悪化しそうなら、できるだけ早く装具を着用するのが望ましい」と話す。そうすれば、7割以上の確率で進行を食い止められる。
装具に伴う支障 後部の面ファスナーなどで1人で着脱できる。球技や徒競走、マラソンなどは、着用したままでも、ほぼ支障なくできる。イスに腰掛けるのも問題ないが、骨盤部を覆うため、床に座る動作などは困難な場合があり、学校での配慮が求められる。